第二章 個人のイニシアチブが社会を造り直す
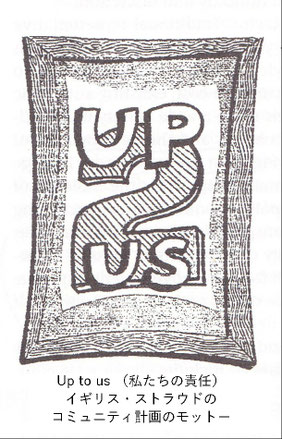
マーテイン・ラージ著、林寧志訳 © 2019 Yasushi Hayashi
『三分節共栄社会―自由・平等・互恵・持続可能性を実現する―』2の1
旧来の旧来の社会構造の力が衰えるにしたがってますます多くの人々がコミュニティや職場で、あるいは地球全体のために自ら変化を促したいと思うようになっています。昔ながらの社会・経済・文化の形態が地球規模で崩れる中で、個人が自発的に行動するという状況が生まれつつあります。これは「お上が/責任者が何とかすべきだ」と考える、伝統的社会構造のもつ依存形態から、各人が自ら変化を促すべく運動を発起、あるいはそれに参加する社会へ、人類史上の重大な変化が進んでいることを表しています。「自ら変化を促したい」という意識が〝ウイルス〟のように、旅行・インターネット・商業活動・グローバルな市民界の誕生を通じて地球全体に広まっています。例を挙げると、西パプアの長老がインドネシア当局と鉱業会社に対抗する原住民の独立運動について講演するのを私は聞いたことがありますが、そこには命がけで秘密のうちに西パプアの実態を映像化するのに成功した若い映画製作者二人がありました。またアメリカ初の黒人大統領が誕生した経緯もその一例です。オバマ氏はシカゴの南部で地域活動家として三年間働いたのちに法律と政治にかかわっていきました。
この章のねらいは性別・階級・職業・民族などに基づいて形成されてきた集団意識から、伝統的な役割分担から解放された個人意識へと移る、地殻変動のような大きな変化を描くことです。ここで二十世紀の歴史の復習をするわけではありませんが、時代遅れとなった民族主義や宗教的原理主義といった集団意識に基づくアイデンティティに解決法を求める動きがあるのは、つまるところ急速に変化する世界において個人の自由がもたらすことへの恐れを発現しているのではないでしょうか。集団意識から自己責任に目覚めた個人意識への歴史的変化はこれからもますます進んでいくでしょう。この意識変化は創造性・平等・正義・持続性を基にする社会建設の礎の一つでもあります。企業・政府・市民界のリーダーたちにとってこの意識の変化を正しく理解することが必要不可欠です。人々は「納まるべきところに納まる」というふうに考えなくなりました。私たちはもはや当局が望むように行動したり行動を控えたりする必要がないのです。
この意識変化に気付いた有能な企業経営者は、時代遅れの「X理論」の前提である階層的統制に納まる労働者観を捨て去っています。
訳注:X理論はダグラス・マグレガーが提唱した経営手法の分類法で、「人間は本来なまけ物で、責任を避けたがり、放っておくと仕事をしなくなる」という考えに基づく、命令や強制で管理する経営手法を指し、Y理論は「人間は本来自己実現のために自ら行動し、進んで問題解決に取り組む」という考えに基づく、労働者の自主性を尊重する経営手法のこと。
以前は出社時に従業員は入り口に頭脳を置き去りにして、言われたとおりの仕事をし、自分の意見は持たないことになっていました。このようなきつい管理制度は基本的に、従業員は勝手で怠け者であり、仕事をするのはカネと地位のためで、責任を取るのを嫌がるという前提に立っていました。けれども、現在成功している企業は、労働者が決定プロセスに関与して、自己啓発や責任のある仕事への従事を望み、自社が社会貢献することで、仕事の意欲を得るということに気付きました。先進的な企業ではすでに従業員参加や柔軟な雇用条件・学習機会・責任・自律・自由裁量などを積極的に進めています。
このような変化は政治部門でも起こっています。伝統的な代表制民主主義による政府は一定期間ごと[イギリスでは五年ごと]に投票によって民意を示した後は、国民は代議員が作った諸政策に素直に従うことを想定してきました。けれども現在では、政界の頂点にある政治家は、〝皇帝〟のように権威主義的に政策を断行すると国民の反感を買うので、それを避けたいなら、国民参加型の民主的プロセスによって問題を分析し、実現可能な解決策を立案しなければならなくなっています。そうでないと国民は「押し付けだ!」と言って抵抗するでしょう。服従の時代は終わったのです。例はいくつもありますが、例えばイギリス国民の多くは、政府がロンドン・ヒースロー空港新滑走路建設を支持するのは、炭素削減の公約と公平で手頃な交通機関の整備という政策に反したものだと考えました。四千人にものぼる反対派の住民はイギリス空港会社が滑走路建設に必要な一エーカーの土地を細かく分けて買い占めるという独創的な作戦を展開しました。これによって政府は滑走路建設を進めるならば時間と経費をかけて用地の強制買収を四千人の住民に対して行わなければならなくなったのです。
この章ではどのようにこの意識変化が起こり、個人や社会変革に対してそれがどんな意味を持つのかを検討し、以下の項目について考えます。
· 祝福を受けた不安:運動を起こすというグローバルな運動
· 個人の潜在能力に目覚める
· 文化創造派が増える
· 集団から個人への転換:社会の基本法則
· かかわることと市民的不服従
· ビジョンを描く
